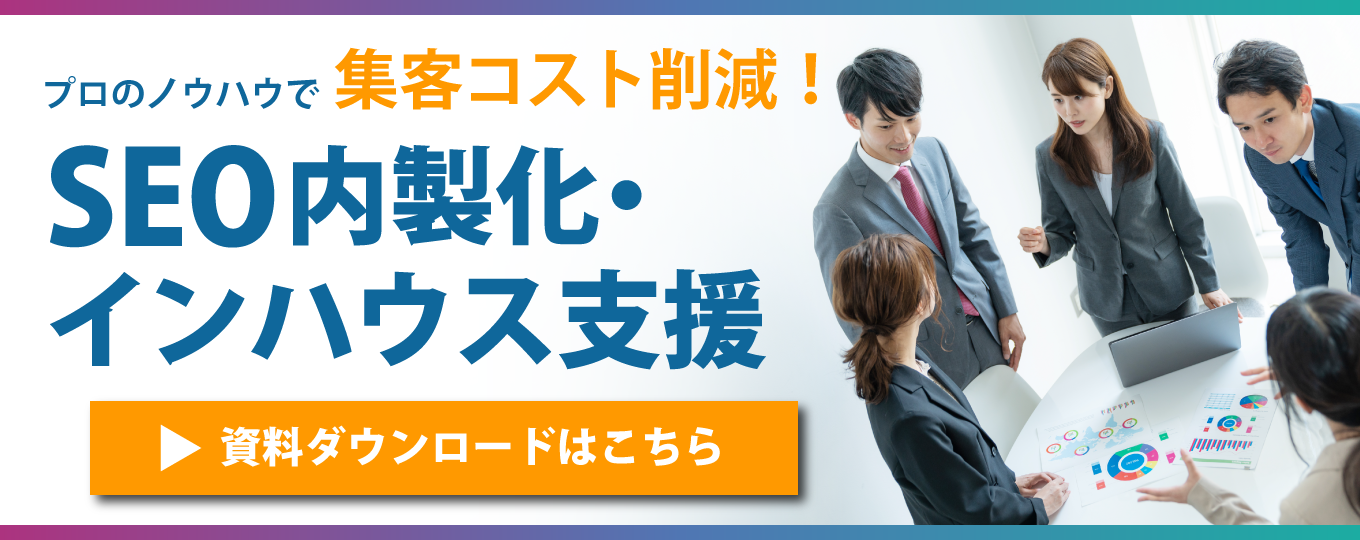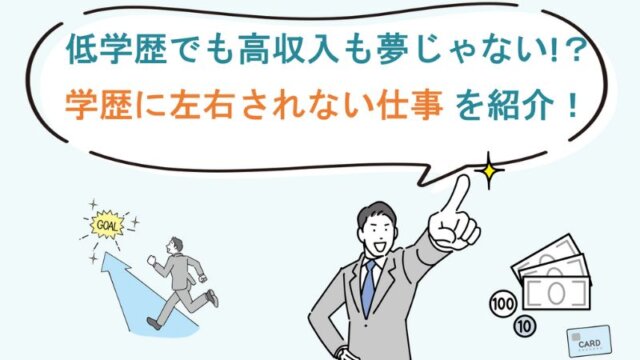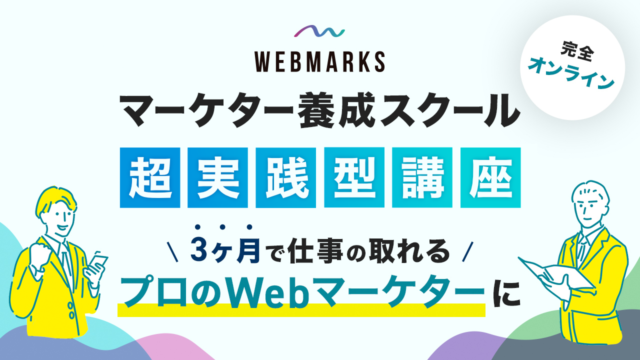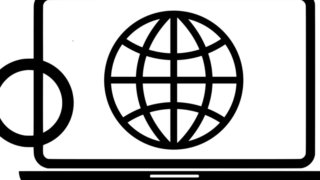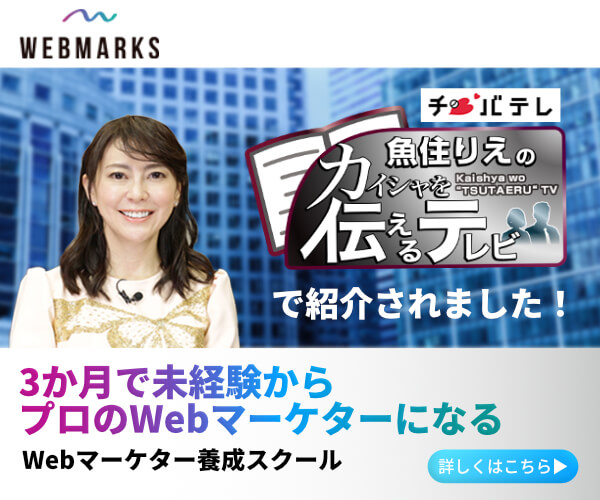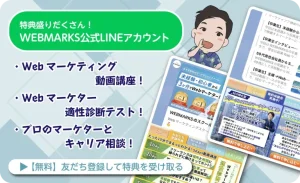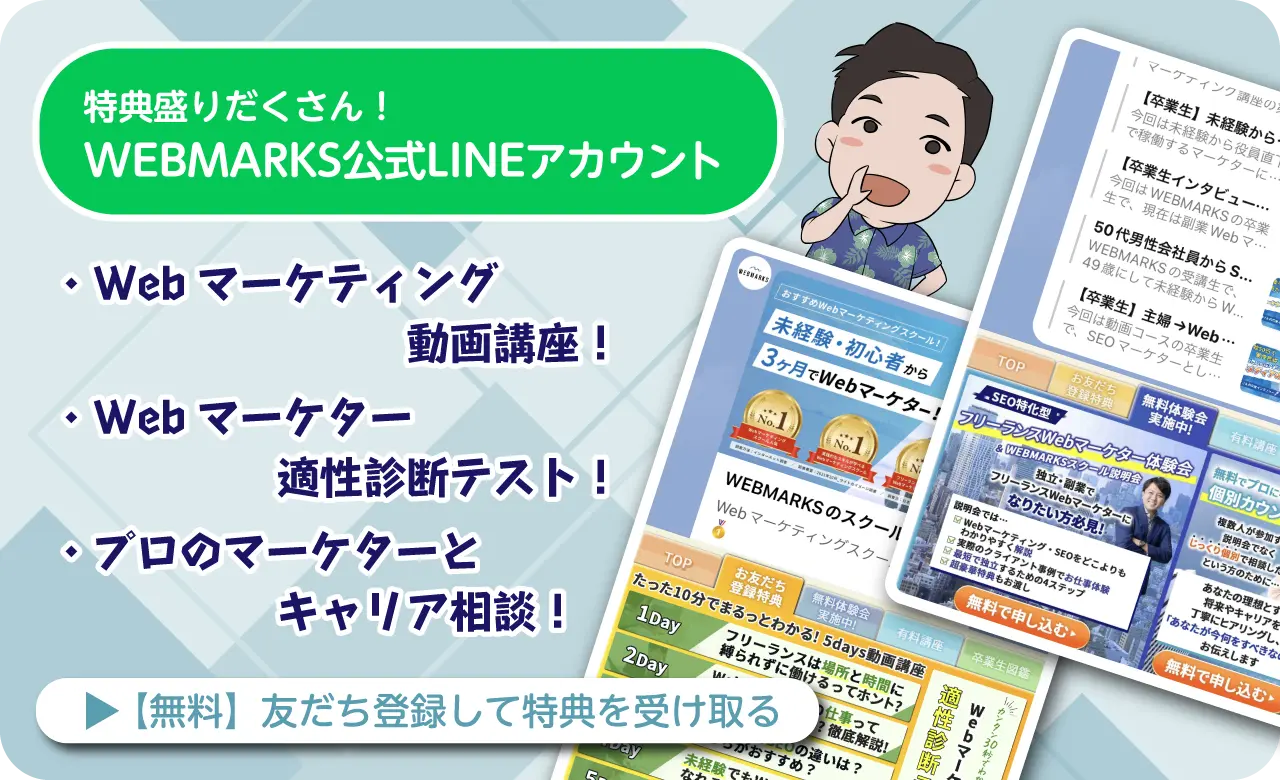サラリーマンからフリーランスとして転向する場合、どのくらい収入が変わってくるのでしょうか。
フリーランスになると、経費や納税関係などの処理を自分で行わなければなりません。
そのためにも、支払うべき税金にはどんなものがあるか把握して節税対策を考えましょう。
Contents
フリ―ランス(個人事業主)の払う税金とは
フリーランスになるということは、会社などに所属しないで個人で企業などと契約して仕事をするという立場になります。
フリーランスに転向すると、「給与所得者」とは異なり「個人事業主」になります。
この「個人事業主」となることで、税法上の扱いが変わってきます。
給与所得者の場合は、必要な経費等は会社が負担しますので給与から引かれるわけではありません。
しかし、「個人事業主」となって得た収入すべてが所得となるわけではなく、総収入額から必要経費を引いたものが「事業所得」となります。
この「個人事業主」の場合、必要経費は控除が認められています。
さらに、個人事業主であれば「青色申告特別控除」を利用することができます。
「青色申告特別控除」を受けることができれば、所得額から所得控除額65万円もしくは10万円を差し引いて計算することになりますので、手続きは大変かもしれませんが、節税するためには大きなメリットとなります。
「個人事業主」が青色申告する際には、開業届を出している必要があります。
まず、フリーランスに転向を考えている方は、開業から1カ月以内に開業届を税務署に提出しましょう。
開業届を提出していると、確定申告の時期に税務署から申告書類が送られてきますので、申告の手続きができます。
このように、開業届を提出していないと確定申告ができず控除が受けられなくなり損をすることになります。
こういった節税効果を受けるためにも、支払う税金について知ることが大事です。
ここでは、フリーランス(個人事業主)にとって必要な税金の種類を解説していきたいと思います。
フリーランス(個人事業主)が納める主な税金として、以下の4つがあります。
- 所得税
- 消費税
- 住民税
- 個人事業税
また、フリーランス(個人事業主)になると、国民年金保険料や国民健康保険税を自分で払うことになります。
では、納める税金について詳しく解説していきたいと思います。
所得税
所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。
フリーランス(個人事業主)の場合売上から必要経費を引いたものが所得(事業所得)となります。
また、所得控除とは、控除の対象となる扶養親族が何人いるかなどの個人的な事情を加味して税負担を調整するものです。
消費税
消費税とは、主にすべての商品やサービスの売り上げを課税対象とし、消費一般に対して負担する税金になります。
また、フリーランス(個人事業主)前々年の課税売上高が1,000万円を超える場合、その年は消費税の納税義務がありますが、1,000万円以下の場合納税義務はありません。
住民税
住民税とは、地方税のひとつで、都道府県が徴収する都道府県民税と、市町村が徴収する市町村税の2つがあり、個人・法人に対して課されるものです。
また、フリーランス(個人事業主)は確定申告をしておけば、住民税は自動的に決定します。
個人事業税
個人事業税とは、地方税のひとつで、都道府県に対して納付するもので、対象となる70の業種が絞られていて、控除額が所得税と異なっています。
個人事業税の税額は所得額から控除額(290万円)を引いた金額に税率がかけられます。
控除額が290万円となっていますので、所得額が290万円に満たない場合、個人事業税は課されません。
国民保険税(料)
国民保険税は国民保険に加入している人(被保険者)を対象に、国民保険に要する費用に充てることを目的として、課する地方税になります。
また、市町村が地方税の規定によらず保険料を徴収する場合や、国民健康保険組合が保険料を徴収する場合は、国民健康保険料と呼びますが、保険税方式を採用している自治体でも、納税者向けの納付書類では「保険料」と称していることがあります。
そして、40歳から64歳の方は、介護分として介護保険料に相当する額が国民健康保険税額に含まれています。
国民年金保険料
国民年金は、日本国内に住んでいて厚生年金保険に加入していない20歳以上、60歳未満の方が対象で、すべて国民年金の第1号または第3号被保険者になります。
そして、40年間全期間保険料を納めた人には、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。
フリーランスの場合ですと、この国民年金のみの受給となってしまい、受け取ることができる年金額は平成30年度ではおよそ年額77万9300円となっています。
サラリーマンとフリーランスの違いとは
フリーランスとして、支払う税金等について解説してきましたが、通常サラリーマンが支払う税金等と大きく異なるのは、個人事業税になると思います。
サラリーマンは、給与から所得税が引かれて手取りとして手元に入ることになりますが、フリーランスの場合売上から必要経費を引いた所得に対して個人事業税がかけられます。
この点が大きく異なりますので、必要経費をしっかり計上しなければ損をしてしまうことになりかねません。
節税するためには、必要経費はしっかり管理しなければなりません。
次からは、具体的な節税方法として税金の計算の仕方を解説していきたいと思います。
フリーランスとしての税金計算
給与から所得税など必要な税金等が引かれている、サラリーマンと違いフリーランスとなった場合、税金の支払いなどお金の管理は全て自分でやらなければなりません。
必要経費をうっかり計上し忘れてしまったなんてことになったら、自分の収入が減ってしまうことにもなります。
そうならないためにも、必要な計算方法を把握して確定申告を行いましょう。
確定申告のための所得計算方法
フリーランスの場合の所得の計算方法は以下のようになります。
総収入金額-必要経費=事業所得額
確定申告での収入
ここでいう総収入金額とは、国税庁の定義では
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。ただし、不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得や山林所得になります。
※参照 国税庁 No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)
となっており、
確定申告書B(個人事業主用)の「所得金額等」の欄は、以下のようになっています。
- 事業(営業等、農業)
- 不動産
- 利子
- 配当
- 給与
- 雑
- 総合譲渡
- 一時
確定申告での経費
そして、必要経費とは以下のようになっています。
必要経費とは、
1. 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
2. その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
※参照 国税庁 No.2210 やさしい必要経費の知識
具体的な経費として、青色申告決算書に指定されているものが、
| 仕入金額 | 租税公課 | 荷造運賃 | 水道光熱費 |
| 旅費交通費 | 通信費 | 広告宣伝費 | 接待交際費 |
| 損害保険料 | 修繕費 | 消耗品費 | 減価償却費 |
| 福利厚生費 | 給料賃金 | 外注工賃 | 利子割引料 |
| 地代家賃 | 貸倒金 | 雑費 | 専従者給与 |
以上のようになっています。
その他の以下のような経費については空欄に記載するようになっています。
| 会議費 | 図書費 | 研修費 | 支払手数料 |
| 支払報酬 | 諸会費 | 車両関連費 | リース料 |
そして、確定申告書B(個人事業主用)の所得から差し引かれる金額(控除額)としては、以下の記載になっています。
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寄付金控除
- 寡婦、寡夫控除
- 勤労学生、障害者控除
- 配偶者(特別)控除
- 扶養控除
- 基礎控除
節税のためにも、このように申告書に記載する項目をしっかり把握して記入漏れのないように申告しましょう。
具体的な年収とは
フリーランスとなると、収入や控除、経費など計算しなければならないものが多く、具体的な手取りの収入がいくらになるのか気になるところです。
ここでは、具体的な例としてフリーランスで働く男性とサラリーマンとして働く男性の手取りの収入を比較して計算してみたいと思います。
例:基本情報)
・ 東京在住の40歳未満の独身男性
・ 年収400万円
まずは、年収400万円のサラリーマンの手取りの金額を求めるために、控除される社会保険料を求めます。
健康保険料+厚生年金保険料+雇用保険料=社会保険料
201,960円+373,320円+12,000円=587,280円
となり、控除される社会保険料の金額は
587,280円
になります。
そして、次に住民税を求めます。
住民税は住んでいる地域によっていくらか違いはありますが、「所得割」と「均等割」との2つに分けて計算されています。
「所得割」
課税所得×(都道府県税4%、市町村税6%(一部例外あり))
「均等割」
都道府県税 1,000円~2,000円 市町村税 3,000円~4,000円
東京都の場合は、この「所得割」が10%、「均等割」が5,000円とそれぞれ決まっています。
住民税額を求めるには、以下のような式になります。
均等割額+(総所得額-基礎控除-給与所得控除-社会保険料)×10%-調整控除=住民税額
均等割額は上記の5,000円、基礎控除額が33万円、給与所得控除額は360万円~660万円以下だと、(収入金額×20%+54万円)になるので、134万円、社会保険料が上記で算出した587,280円となります。
そして、調整控除額として2,500円になります。
上記の式にそれぞれ当てはめてみると、
5,000円+(400万円-33万円-134万円-587,280円)×10%-2,500円=176,700円
となり控除される住民税は
176,700円
になります。
最後に、課税所得金額を求め、復興特別所得税分を計算します。
課税所得額は、総所得額から、基礎控除、給与所得控除、社会保険料を引いた金額になります。
総所得金額-基礎控除額-給与所得控除-社会保険料=課税所得金額
400万円-33万円-134万円-587,280円=1,692,000円
※課税所得額は1,000円未満の端数は切り捨てになります。
課税所得額は、
1,692,000円
になります。
この金額に所得税率5%をかけると84,600円になります。
さらにこの金額に、復興特別所得税2.1%を上乗せすると
86,300円
になります。(100円未満は切り捨てになります。)
上記で求めてきた金額を総所得金額から引いたものが手取りの金額となります。
- 社会保険料 587,280円
- 住民税 176,700円
- 復興特別所得税 86,300円
総所得金額-社会保険料-住民税-復興特別所得税=手取り金額
400万円-587,280円-176,700円-86,300円=3,149,720
このように、年収400万円で控除等を引いたおよそ315万円がサラリーマンの手取りの金額になります。
では、同じ条件の男性がフリーランスとして働く場合、同じ手取り金額になるにはどのくらいの事業所得があればいいのでしょうか。
求めたい事業所得額をAとして計算していきたいと思います。
事業所得額Aから以下の控除額を引いた金額が先ほどの315万円以上になるように計算していきます。
- 個人事業税
- 国民年金保険料
- 国民保険料
- 住民税
- 所得税
- 復興特別所得税
まずは、先ほどと同じように上記の控除額を求めていきます。
●個人事業税額=(A-事業主控除290万円)×5%=(0.05A-145,000円)
●国民年金保険料=16,340円×12カ月=(196,080円)
●国民健康保険料=基礎分+支援分={均等割額39,000円+(A-基礎控除33万円)×7.32%}+{均等割額12,000円+(A-基礎控除33万円)×2.22%}=(0.095A+19,518円)
●住民税額=均等割額5,000円+(A-基礎控除33万円-青色申告控除65万円-国民健康保険料-国民年金保険料-個人事業税額)×10%-調整控除2,500円=(0.08546A-102,559.8円)
●所得税額=(A-基礎控除38万円-青色申告特別控除65万円-国民健康保険料-国民年金保険料-個人事業税額)×所得税率-控除額=(0.00189466A-4,358.7558円)
●復興特別所得税額=所得税額×2.1%=(0.08546A-207,559.8)
こちらの控除額を計算すると、
A-{(0.05A-145,000円)+(196,080円)+(0.095A+19,518円)+(0.08546A-102,559.8円)+(0.00179466A-4,358.7558円)+(0.08546A-207,559.8円)}≧315万円
となり、まとめると、
A≧4,261,889円(小数点以下切り捨て)
以上のように、年収400万円のサラリーマンと同等以上の手取りを求める場合、426万円以上の事業所得が必要になります。
この金額は必要経費が入っていない金額になりますので、経費のことも考えなければなりません。
自分にスキルがあり、これ以上の収入が得られる可能性があるならば、サラリーマンとして働くよりもフリーランスで働いた方が稼げるということになります。
まとめ
サラリーマンとしての収入とフリーランスとして収入を得る場合を比較してみました。
フリーランスとして働く場合は、サラリーマンと違って必要経費や納税関係といった会計処理を自分でやらなければならなくなり大変なところもありますが、収入の目安としてはこのように比較できます。
サラリーマンからフリーランスに転向を考えている方は是非参考にしてみてください。