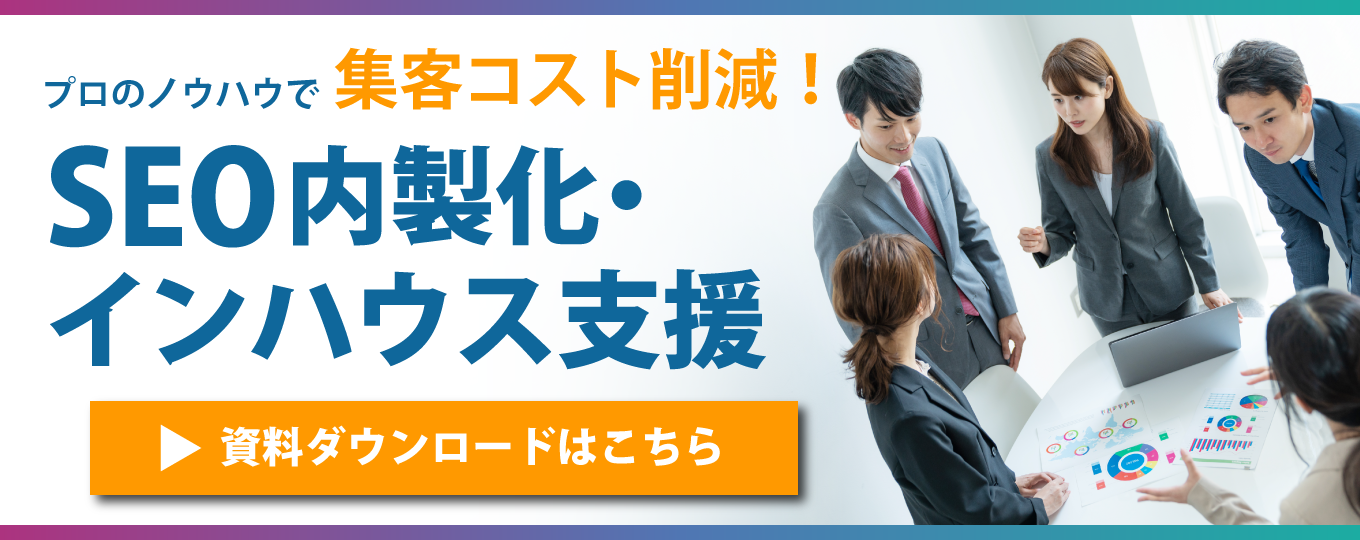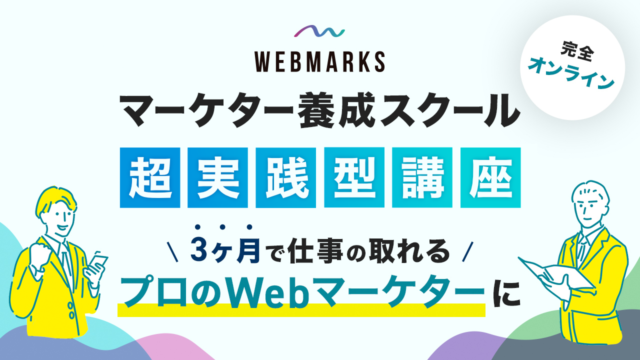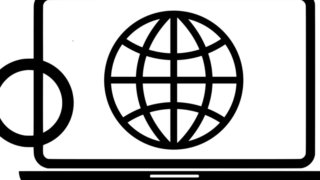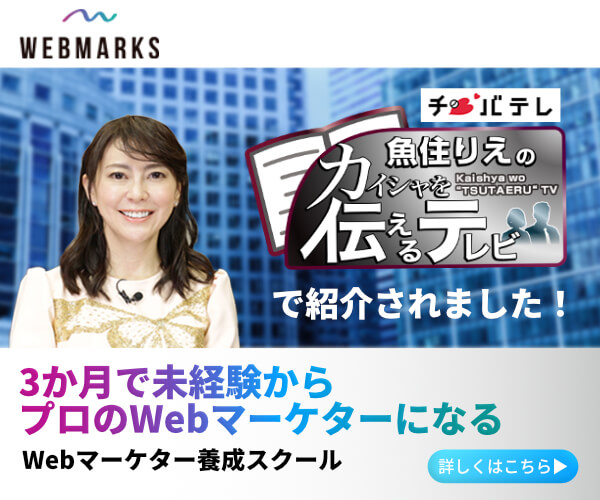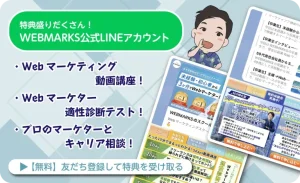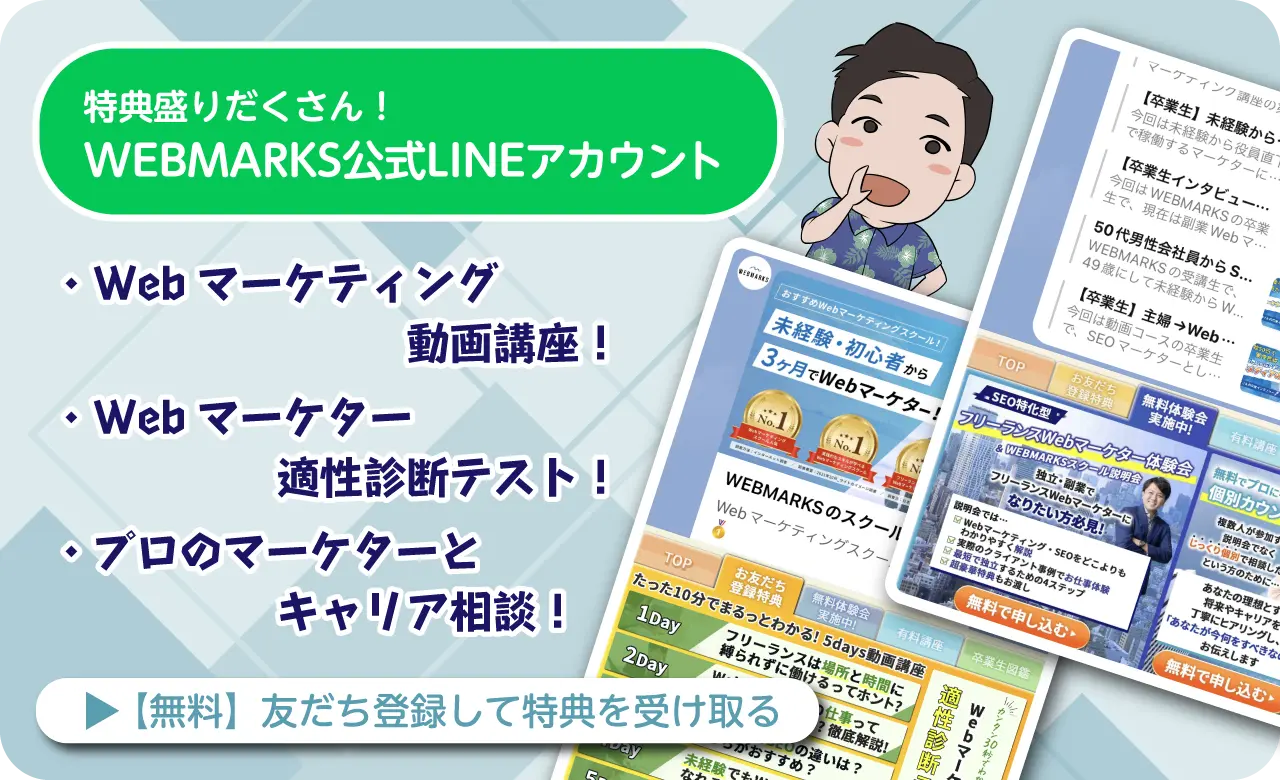SEOに有利な文字数はありません。1記事あたり最低1000文字以上、2000文字以上あれば安心、3000文字以上になれば上位表示が狙える可能性があるといった都市伝説のような情報がweb業界に拡散していますが、それは本当に都市伝説。
悪質なSEO業者が流行らせた根拠のない、でたらめな情報です。10年近く前のまだGoogleの検索アルゴリズムに穴がたくさんあった時代の名残で、今では全く通用しません。
Contents
SEOに文字数が関係しないとGoogleが公表してる

Googleのウェブマスター・トレンド・アナリストであり、SEOの第一人者であるジョン・ミューラー氏は公式に、文字数の優劣を判断する検索アルゴリズムはないと発言しています。
つまり、1記事の文字数が500文字だろうが、2000文字、3000文字、1万文字であったとしても、文字数の多い少ないことだけではSEOの評価には何ら関係がなく、検索順位のアップダウンに影響することはないということです。
SEOを研究している専門家が発言しているのではなく、GoogleでSEOを作っている側の人が発言していますから、その信ぴょう性を疑う余地はありません。
さらに、ミューラー氏は、検索を利用するユーザーにとって魅力的で関連性の高い検索結果であれば、文字数が少なくても、たくさんの画像が使用されていても全く問題ないと発言しています。
このことからも、1記事あたりの文字数は最低何文字以上といった基準とSEOには何ら関係性がないことがわかります。
記事を更新する際に、文字数が少ないからと、特に必要のない情報を追加したり、難しい言い回しで文字数を稼いでみたり、同じ内容を言い方を変えて使いまわすようなことは今すぐやめましょう。
Googleのウェブマスター・トレンド・アナリスト:ジョン・ミューラー氏の発言
翻訳:
私たちはあなたのページの単語を数えて100語までが悪い、100語から500語の間のすべてが大丈夫で、500語以上のすべてを評価するといったアルゴリズムを持っていません。私たちは、ページ全体を見て評価しています。
本当にユーザーにとって魅力的で関連性の高い検索結果(ページ)であれば、長いか短いか、またはたくさんの画像であったとしても、全く問題ありません。
専門性と分かりやすさがSEOに最も影響する

SEOに最も関係するのは文字数ではなく、情報の専門性と分かりやすさだということを、Googleは公式ガイダンスで発表しています。コンテンツガイドライン(公式)
ここで注意しなければならないのは、「情報の分かりやすさ」という点が専門的な内容をわかりやすく簡単な言葉や例を用いて説明するということだけではないということ。Googleの指す「情報のわかりやすさ」とは、その情報に関係するすべての情報を包括的に含めているかという点です。
例えば、料理のサイトを運営していて、肉じゃがの作り方を紹介する記事を書くのであれば、材料、所要時間、コツといった肉じゃがの作り方だけでなく、カロリーや盛り付けに合うお皿の選び方、肉じゃが誕生のヒストリー、男性ウケする料理ナンバー1の理由など、「肉じゃが」に関係するあらゆる情報を掲載することで、Googleはその記事を評価します。
つまり、肉じゃがに関連する全ての情報を網羅することが、GoogleがSEOに反映させる情報のわかりやすさの基準です。
・専門的な情報をわかりやすい言葉で説明する
・関連する情報をできるだけ多く載せる
この2点がSEOに優位に働き、検索順位を上昇させる大きなポイントとなります。
結果として文字数が多くなる
適当なキーワードでGoogle検索をかけ、上位表示されているサイトを見てみると、そのほとんどが膨大なテキスト量で構成されていることがわかります。
この点だけをみると、やはり文字数とSEOには関連性があるように思えてしまいますが、そうではなく、関連する情報をより多く記載しているコンテンツが検索上位表示を獲得しているために起きていることです。
サイト上でメインとなるテーマに沿って記事を書く際、1000文字から2000文字あれば十分にそのテーマの説明ができるとしても、そのテーマに関係する事柄を一つ一つピックアップして補足していくと自然と文字数は増えていきます。
メインテーマ+関連する情報=情報のわかりやすさとして、Googleに評価されますから、結果として記事の文字数は多くなるという構図であって、文字数が多い方がSEOに有利に働いているわけではありません。

なぜ文字数が多いほどSEOに有利と思い込んだのか

とりあえず毎日更新しないといけないから、何でもいいから記事を書いて更新しておけばSEOに有利なはず。そんな思い込みや、根拠のない情報で、やっつけの文章を1000文字くらい書いて更新する。
その時間は、まったくもって無駄でSEOにおいて何ら良い影響を与えません。本来のSEOについて、SEOとSEMの違いとは?の記事で詳しく解説しています。
それでも、今まではそれで検索上位表示が取れていたと実感しているweb担当者の方は多いのではないでしょうか。その背景には、悪質なSEO業者とGoogleの検索アルゴリズムの穴が影響しています。
Googleの検索アルゴリズムは近年、大幅なアップデートを繰り返し急速なスピードで進化していますが、数年前までは欠点が多く、その欠点を利用して成果を上げるSEO業者が数多く存在していました。
その最たる例が、被リンクをたくさんサイトに張り付けて検索順位を上げる被リンク対策。そしてもう一つが、毎日記事を更新することでサイトの評価を上げるといったもの。更新さえすれば中身は希薄でもよく、最低〇〇文字以上の記事をとにかく毎日更新するといった施策で検索順位が上がっているように見えました。
しかし、実際は被リンク対策によって順位が上がっていただけに過ぎず、中身のない更新頻度と文字数稼ぎだけの記事更新はSEOに有利な働きをしていたわけではありません。

文字数ではなく品質を優先するアップデート
文字数や更新頻度だけの低品質なコンテンツで構成されたWebサイトの検索結果の順位を下げ、良質で分かりやすいコンテンツのWebサイトが上位に表示されるようにすることを目的とした、Googleの検索アルゴリズムのアップデートが日本で2012年7月からスタートし現在に至るまで複数回更新され、その精度は更新のたびに正確さを増しています。
つまり、2012年7月までは最低〇〇文字以上の記事を毎日更新することが、SEOに効果的な施策だったということです。これまで通じていた施策だから、今でも有効なはずと思い込んでいるweb業界関係者は多くいますが、全く根拠のない思い込みです。

被リンク対策を通じなくするアップデート
サイトに張られるリンクの品質に関する評価が見直され、中身のない形だけのリンクをたくさん張り付けているWebサイトの検索順位を下げることを目的とした検索アルゴリズムの変更が、2012年4月に実施され現在に至るまで日々更新され続けています。
ペンギンアップデートと呼ばれるweb業界に激震を起こした大きなアルゴリズム変更で、被リンク対策で検索上位表示を獲得していたSEO業者のほとんどが大打撃を受けました。
それまでは、リンク本数が多いというだけでユーザーにとって役に立たないサイトでも上位表示されていましたが、このアップデート以降、リンクの中身まで評価対象とされるようになり検索上位表示獲得に被リンク対策は通用しなくなりました。

まとめ

Googleの検索アルゴリズムアップデートにより、コンテンツの文字数ではなく品質が重んじられるように変わりました。その品質とは、分かりやすさのことで、専門的なテーマをわかりやすい言葉で説明するだけでなく、関連する情報をすべて含めることです。
Googleが公式に文字数はSEOに関係しないと発表していますから、文字数稼ぎの記事を書くことはやめて、ユーザーにとって有益で役立つ情報を更新していくことが最もSEOに効果的な対策です。
・SEOに文字数は関係ないとGoogleが公式に発表している
・コンテンツの専門性と分かりやすさが一番SEOに大切
・上位表示されているサイトは文字数ではなく、関連する情報も載せているから結果として文字数が多い