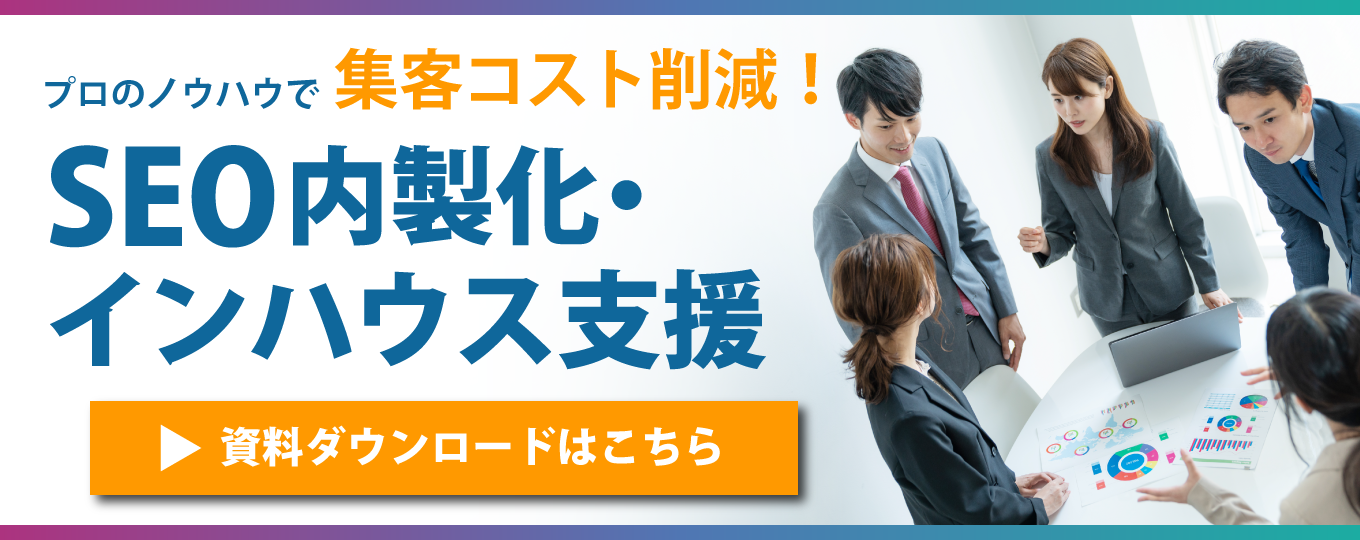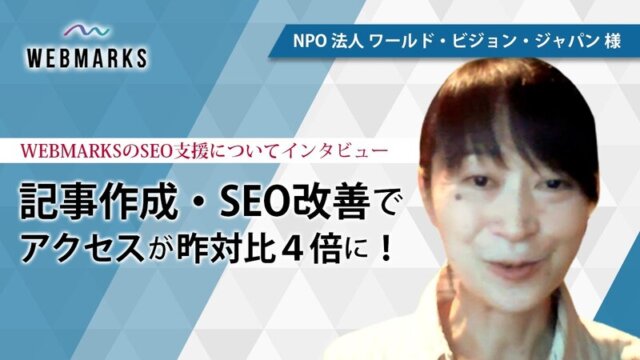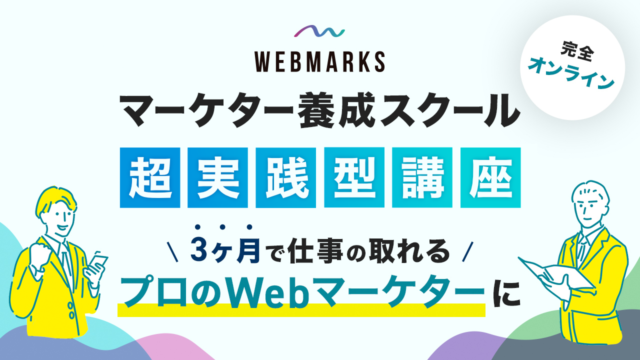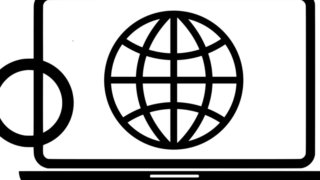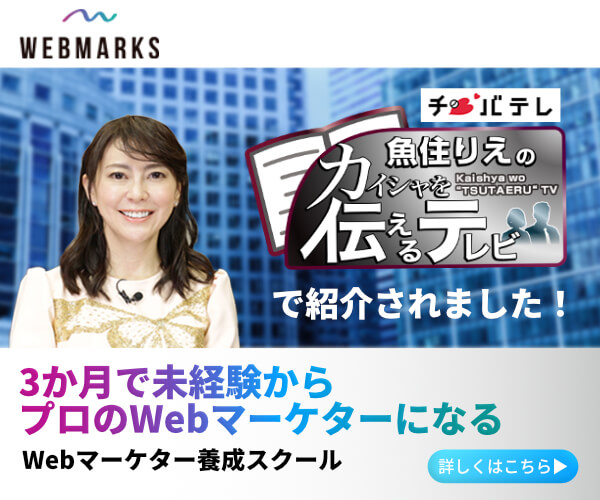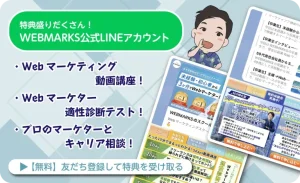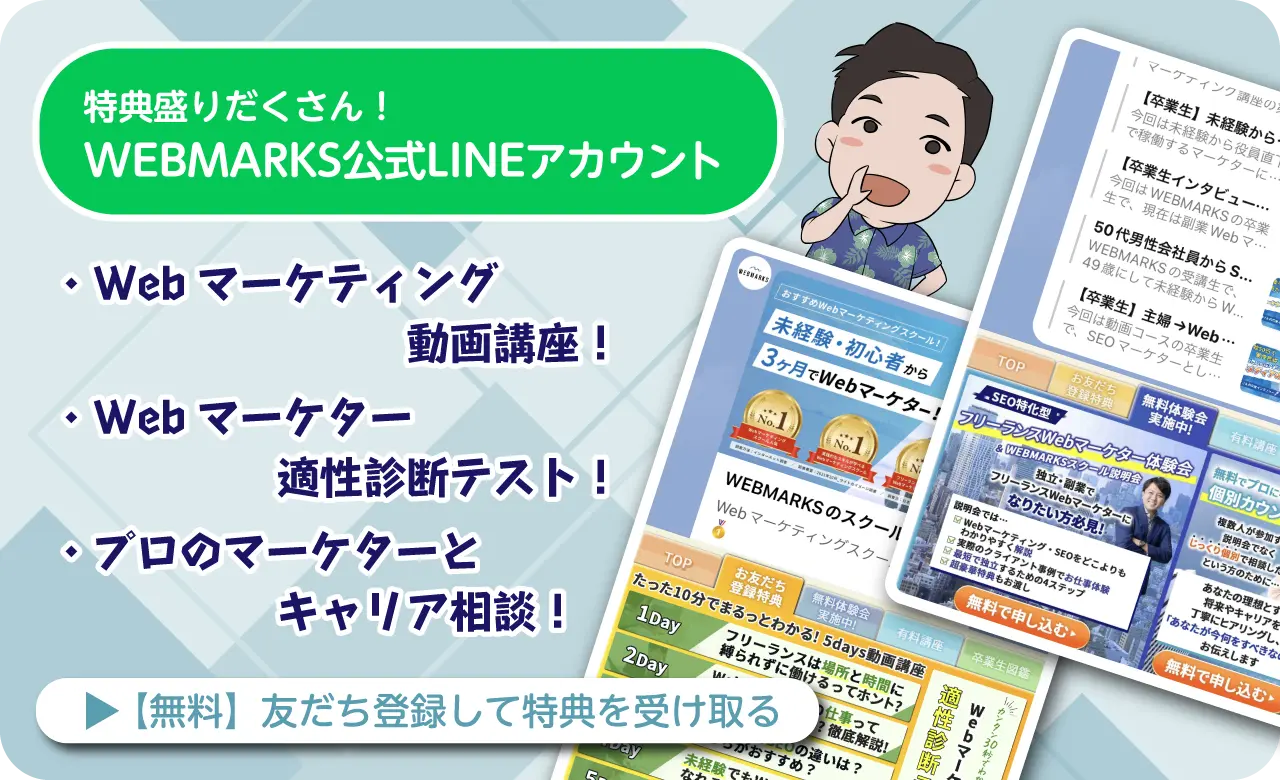- 「Web業務を内製化したいけど外注との違いがいまいちわからない」
- 「内製化するために必要な条件がわからない」
こんな風に思っていませんか?
会社の経営手法の一つとして内製化を取り入れる会社は少なくありません。内製化するにあたってどのようなメリット・デメリットがあるのか、外注との違いは何なのか把握していきましょう。
また、内製化と外注に良し悪しはなく企業の規模や業種によっても異なるため、よく検討する必要があります。
\8週間でSEO担当者を社内育成!/
Contents
Web内製化(インハウス)とは?

内製化とは、外注(外部委託)していた業務を自社内で行うように変更することをいい、インハウスとも言います。例えば、製造工程で一部外部に委託していたものを、全て自社内で製造するように変更することも内製化といいます。
Web内製化とは、ホームページや広告、SNSの運用など、文字通りWebに関する業務を内製化することをいいます。
様々な分野
ひとことでWebを内製化するといってもWebには様々なジャンルが含まれています。プロデューサー、ディレクター、プランナー、マーケター、プログラマー、コーダー、デザイナーといった職種に分かれています。
この中でもさらに分岐するものもあり、例えば、マーケターには広告運用やSEO(検索エンジン最適化)などというジャンルがあります。全ての業務をいきなり内製化するには負担が大きすぎるので、一部を内製化し外注と組み合わせることで高いクオリティを確保することができます。
本記事ではWeb全体について内製化と外注のメリット・デメリットを説明させて頂きます。
\8週間でSEO担当者を社内育成!/
外注のメリット

早速、外注のメリットから見ていきましょう。
最新のノウハウ
その分野のプロに依頼することで最新のノウハウを活かした施策を受けれる可能性が期待できます。また、様々な分野があるWeb関連で、ピンポイントの分野から探せる点も大きいです。自社で育成に労力をかけずにプロのノウハウを活用することができます。
最新の情報を共有してもらうことで競合やトレンドなどの情報を自社で追う手間も省けます。
人件費を抑えられる
社内にWeb担当を置かずに必要な期間だけ依頼することで、継続的にかかる人件費を抑えることが可能です。結果が出なかった場合に別の業者に依頼することも可能なので、雇用しない利点もあります。
広告や記事の作成など、一度作ってしまえば効果が持続するものは何度も依頼せずに済むのでコストを抑えることができます。ただし、内製化でも話しますが、外注にもコストはかかるので単純に安いとは言えません。
第三者目線での施策
自社の業界ではなく、あくまでWeb業界の人が施策することで、普段とは違った第三者目線での意見を取り入れることができます。Webのプロの観点から意見を貰えるので、新しい角度からの考えを取り入れることができます。
\8週間でSEO担当者を社内育成!/
外注のデメリット
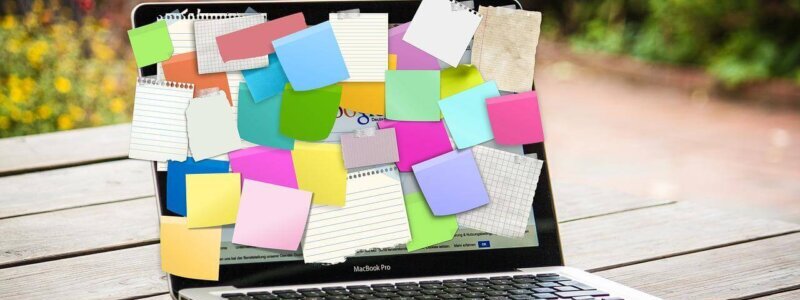
逆にデメリットは何でしょうか。
ぼったくられる可能性
外注した企業や個人事業主等から、不当な金額を請求されてしまう可能性があります。また、業務を実行した企業以外が修正できない設定にされると、追加費用がかかってしまうこともあるので、社内にWebについて詳しい人がいない場合は要注意です。
金額に合わせて質の保証もないことが大きなリスクとなります。
社内にノウハウが残らない
Web担当の人員を設置しない限り、ノウハウが貯まっていかないこともデメリットの一つです。委託した企業から運用や実績のレポートはあっても企業秘密があるため、情報を十分に得ることができません。
対応が遅れることも
代理店や個人事業主では多くの案件を抱えていることもあり、調整や変更といったことが即座に対応されないケースも多いです。また、修正や変更などがあった場合に都度打ち合わせも必要となるので、スムーズにことが進まない可能性もあります。
\8週間でSEO担当者を社内育成!/
内製化するメリット

本題の内製化した時のメリットを外注と比較しながら見ていきましょう。
外部委託にかかるコストを削減できる
内製化にも人件費がかかるため単純に比較は出来ませんが、外注にかかる際の代行手数料や、初期費用、管理費用などを削減できます。高額なコストをかけて定期的に依頼する必要があるため、社内で担当者を置くことで長期的に見て安価となる可能性が見込めます。
スピーディーな対応
担当者が社内にいることで話がスムーズに進み、細かい確認やちょっとした修正など、意思疎通が図りやすいです。外部との打ち合わせに時間をかけずに対応できるのが強みです。
また、緊急時なども必要に応じてすぐに対応できます。反対に言えば、自社に合わせたペースで運用ができます。
自社に合った作り
自社の扱う商材の特徴や魅力を理解している人が担当することで、自社に合った作りを再現できます。このメリットは広告やホームページの作成、運用に大きく影響します。
ノウハウの蓄積
実際に社内で行うことで専門領域でのノウハウが蓄積され、技術・品質レベルが上がることが期待できます。専門的な知識を持つ人材が育ち、その知識が共有されることで会社の財産となります。
一度確立されれば、次の世代、また次の世代へとノウハウがどんどん貯まっていきます。
悪徳業者の回避
社内の人員が業務を行うため、ぼったくられることや質の悪いコンテンツを提供される心配がありません。情報を競合に流されるリスクも自社の管理で行えます。
\8週間でSEO担当者を社内育成!/
内製化するデメリット

続いて内製化のデメリットを見ていきます。
人材の確保
専門性が高い故に人材の確保が最大の難点です。新しく人を採用する必要や、現在いる人に新しく覚えてもらう必要があります。人を雇用することになるため、結果が思うようにでないとしても、簡単に解雇することはできません。
新しく覚えて貰う場合は、講座やセミナーの手配、もしくは独学など、勉強方法の選定から考える必要が出てきます。
体制作り
チームとして作るのであれば、それだけ人材が必要となります。また、一から覚えてもらうにも教育体制を作る必要が出てきます。効果が出るのに時間がかかる分野であるため、専任者を一人置く場合にも周りからの理解を得なければモチベーションにも関わります。
精通していなければ結果を適切に評価することが難しいこともあり、専任者を置ける体制作りに時間がかかってしまいます。様々な負担が考えられます。雇用や教育の仕方によっては人件費が高くなる場合も考えられます。
専門知識が求められる
内製化を始めるにあたって知識の無い人を採用してから身に着けてもらうには育つまでに時間や労力がかかります。育つまで待てる企業であれば問題ありませんが、そうでない場合は「専門的な知識」を身に着けた人材を採用しなければなりません。
それも自社の求める役割についての知識を持った人材、もしくはオールラウンダーな人材を獲得する必要があり、採用条件も厳しくなってしまいます。
一つの業界の知識に偏る
自社に関わる業界の知識に偏ることがデメリットと言えます。業界に精通することは良いことですが、Web業界では様々な分野の流行に影響を受けるので、一つの業界に偏った知識では後手を踏んでしまう可能性が高いです。自社の専属として働く上に他の分野の情報も取り入れようとすれば負担が大きくなってしまいます。
\8週間でSEO担当者を社内育成!/
Web業務を内製化するには

社内での理解
Web関連の業務を始めるにあたって、その業務が自社のビジネスにどのようなメリットがあるのか、どのような目的があるのかを明白にし、重要性を社内に周知、理解してもらう必要があります。
相応の労力をかけても効果が現れるのに時間がかかることもあり、Web業務は見かけよりも難しいものです。こういった点を周囲が理解していなければ担当者のモチベーションや周りからの評価にも悪影響が出てしまいます。
まずは、目的を明確にし、Web業務の重要性と難しさを社内全体に周知し、メディアやコンテンツの価値を理解してもらいましょう。
専任者を置く
専門的な知識を持つ人材を雇った場合や、人材が育った後に限りますが、Web関連の業務では多くの作業をこなさなくてはならないため、分野によっては兼業も可能かもしれませんが、基本的に専任者を置くと良いでしょう。
継続的に成長していくため、一人で孤立して行うよりはチームでの業務が理想であり、どの分野にしろ幅広い知識が必要になってくるため、リーダーとなる専任者を置くことで円滑に組織形成を行うことができます。
専任者にはライティングやマーケティングのスキルの他に、スケジュール管理やマネジメントなどの作業も含まれるため、かなりの量の仕事をこなす必要があります。専任者を置いてクオリティを確保しましょう。
情報収集
Webを内製化するにあたって、外部からの情報は必要不可欠です。専門業者に外注する場合は最新の情報を共有してくれますが、内製化する場合は自社だけで積極的に情報収集しなければなりません。
特にマーケティングではユーザーのトレンドの変化など、移り変わりの激しい分野では最新情報のキャッチアップが欠かせません。常に最新の情報をキャッチアップし、臨機応変に対応することが求められます。
\8週間でSEO担当者を社内育成!/
SEOを内製化する

ある程度の規模を持つ会社や、規模が小さくてもWebの内製担当者を適切に評価できるような環境であれば、内製化のメリットが多いと考えています。IT業界でない限り、人材や継続的な仕事の確保といった面で、規模が小さい会社はリスクがあることを理解しておきましょう。
ただし、全てを内製化するのではなく、Webマーケターを自社に置き、デザインやエンジニアリングを外注するといった手段も選択できます。
2ヶ月でSEOマーケターを育成
マーケターの一つとしてSEOマーケターがあります。SEOとは検索エンジン最適化のことで、マーケターの主な業務として、以下の業務があります。
- ユーザーニーズを満たすコンテンツの作成
- 検索エンジンに評価されるサイトを設計する
良質なコンテンツであればSNSや広告の運用がなくとも継続的な集客が見込めます。WEBMARKSでは2ヶ月でSEO担当者を社内育成するプログラムを実施しています。他ではないSEOに特化した講座で、現役プロのWebマーケターが直接指導することで2ヶ月という短期間でSEO担当者の育成を可能にしています。
企業の内製化を成功させたい場合は、法人様におすすめのSEO研修の記事もあわせてご覧ください。
成果につながる研修の選び方とともに、SEO研修の費用や内容について詳しく紹介しています。
まとめ
即時に効果が欲しい場合は外注を選んだり、人件費に余裕があり育成までの時間が待てるのなら内製化を取り入れたりと、向き不向きはあっても一概に良し悪しをつけることはできません。企業の規模の大きさや、効果が期待できるまでの期間や資金的余裕など、自社に合ったやり方を模索する必要があります。
折衷案としてSEOマーケターを社内に置くことで、マーケターがWeb担当者となり、他を外注し、効果が出るようなら他の内製化も進めてみてはいかがでしょうか。
\8週間でSEO担当者を社内育成!/